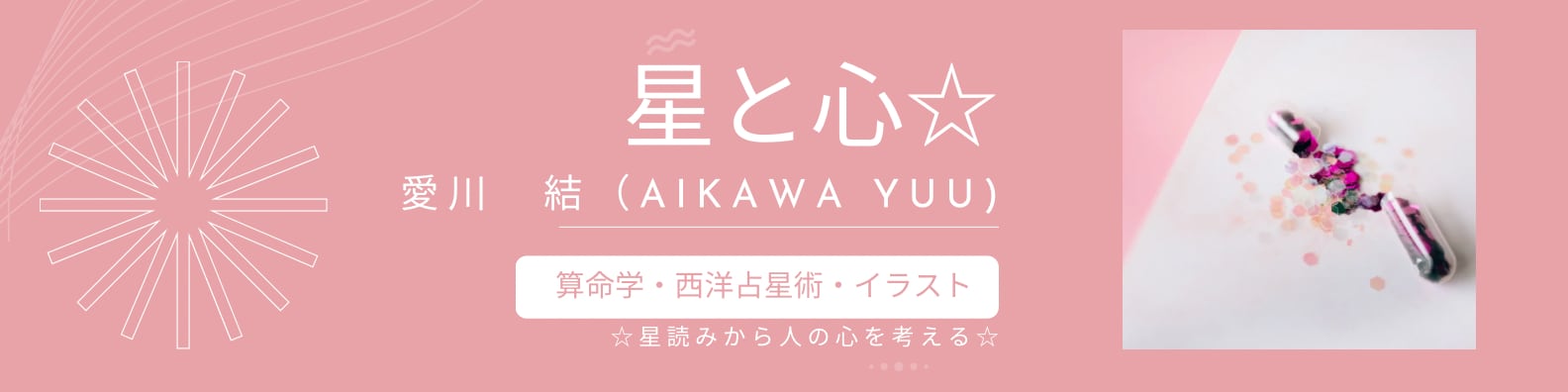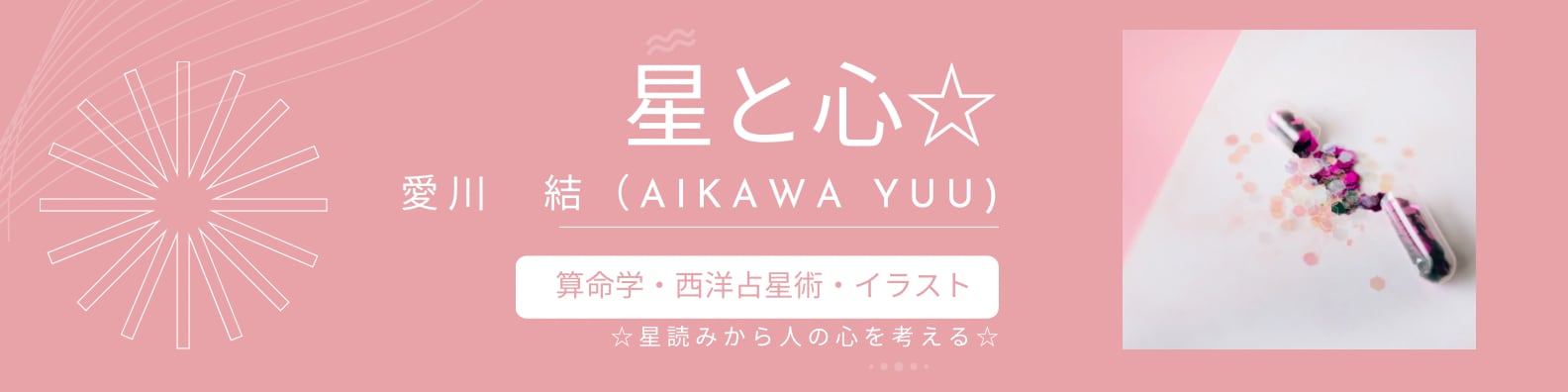2024/09/05 17:52
先日のアンケートの補足です。
↓ ↓ ↓
「・独学で算命学を勉強しています。位相法がなかなか覚えづらく、
モヤモヤしておりました。」
というお答えがありましたが
位相法(いそうほう)に
ご興味を持っておられる方、勉強したい方は
結構いらっしゃるようですね。
こちらでも、位相法の記事はアクセスが多いです。
↓ ↓ ↓
何のために占いを勉強するのか、
占ってもらいたいのか、というと
自分(または周りの人)の性質
人間関係の悩み(相性)
時期的な問題
などを
占いではどうみるのか?
を知りたいと思ったからですよね、きっと。
位相法はそんな時、
力になってくれる心強い味方☆です。
命術を学ぶのは時間がかかる、と
先日も書きましたが
位相法も
いきなり分かる人は
そう多くないはずです。
今はどうかわからないけど、
小学校の、九九(くく)を覚えた時だって
一の段、ニの段、三の段、…と、順を追って
ひたすら口に出して暗記していったはず。
登校してから
朝、ストーブを囲んでみんなで呟いて、
授業でも音読して。
家に帰ったら
親に聞いてもらいながら
「今日はここまで言えた!」
と…。
そうやって
少しずつ覚えていったっけ…。
(半世紀前の遠い記憶)
そして、暗記とは別に
授業で「なんでその答えになるのか」
という
意味や仕組みを習った記憶があります。
位相法も同じ要領で、
1)口にだして暗記する
例:三合会局(さんごうかいきょく)ならば、
「申子辰(さるねたつ)・三合水局(さんごうすいきょく)、
亥卯未(いうひつじ)・三合木局(さんごうもっきょく)、
寅午戌(とらうまいぬ)・三合火局(さんごうかきょく)、
巳酉丑(みとりうし)・三合金局(さんごうきんきょく)」
と、ひたすらぶつぶつ唱える。
意味はわからなくても、音で覚えると
そのうち「あ、これだ」と
漢字も一緒に思い浮かぶようになるはず♪
(講座をやっていた時、受講生さんの中には
冷蔵庫に表をコピーして貼って、家事の合間に
ひたすら呟いてた方もいらっしゃいました)
2)実際に自分で位相法を体感してみる
おすすめの方法としては
日々、位相法を見て検証するのもいいのですが、
細かすぎて
実感できないことが多いかもしれません。
そこで、
講座を開催していた時に
受講生の皆さまと一緒にやったワーク。
「自分年表」を作って、
自分の命式(宿命の陰占六文字)に対して
その年に成立していた位相法(もちろん天冲殺も)
を見ながら
どんなことがあったか、どんなことを感じたか
その理由を探ってみる、という作業をやりました。
これ、結構
「この位相法があったから、この時こうだったのか!」
と気づくことがあって、おすすめです。
時間はかかりますけど、やる価値ありますよ〜☆
※ただし、宿命冲殺をお持ちの方は
あまりハッキリとは
位相法の力を感じにくい場合もあるようです。
何にしても
学びに近道はありません。
(※一回見たら覚えるような天才は別として。
そして「効率のよい学び方」というのは
あるとは思うけれど。普通は時間がかかります)
焦らずに
楽しみながら、
自分の人生の謎を
ひとつひとつ
「占い」という視点から
解き明かしてみませんか。
楽しいですよー♪
この楽しみは
いわゆる「沼」にハマる、という奴ですね。
ここを読んでくださっているのは
きっとそんな
占いの「沼」にハマった方、
または
ハマりつつある方だと思います♡
(違ったらごめんなさい)
他の人には理解されにくいかもですが
ぜひご一緒に、この細い沼地を
それぞれのペースで歩いて行きましょう☆
愛川 結
【位相法・記事一覧】
(いそうほう)・その1
(いそうほう)・その2(ほうさんい)
(いそうほう)・その3(さんごうかいきょく)
(いそうほう)・その4(はんかい)
(いそうほう)・その5(しごう)
(いそうほう)・その6(たいちゅう)
(いそうほう)・その7(てんこくちちゅう)
(いそうほう)・その8(がい)
(いそうほう)・その9(けい)
(いそうほう)・その10(は)
(いそうほう)・その11
↑
ここで、自分の命式に対しての
見方を書いていますが、
もう少し具体的に、例を出しています。
時期について、また、相性について、
位相法を実際に使って読もう!
と思ったとき
初心者の方が悩みがちな
「こんな時はどう考えるのかな?」
という例を載せています。
宜しければ、ご利用くださいませ☆
星と心☆愛川 結